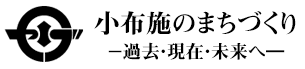旧石器時代から存在した人々の暮らし
小布施の歴史は、約1万年前の旧石器時代にさかのぼります。町の東側、雁田山沿いで発見された「赤はげ遺跡」からは、小布施最古の遺物といわれる石器が出土しており、狩りが中心だった時代からこの地に人間の生活が存在していたことを伝えてくれます。
また、縄文時代の土器や石器も複数出土しており、旧石器時代だけでなく、その後の時代にも、継続的にこの地に人々の暮らしが存在していました。
重要な戦略拠点だったことを伝える大規模な山城跡
中世の時代には、雁田山周辺に苅田城、滝ノ入城、二十端城などの山城が築かれ、この地域における重要な戦略拠点となっていたと伝えられています。これらの山城跡は、現在でも雁田山ハイキングコース沿いにその面影を見ることができます。
松川によりつくられた「扇状地」と、果樹の町
現在の小布施の地図を見てみると、東に雁田山、西に千曲川、北に篠井川、そして南に松川が流れ、四方を山と川に囲まれた地域であることがわかります。このような地形を形づくる上で、特に重要な役割を果たしたのが松川です。
小布施は、松川が長い年月に氾濫を繰り返すことで「扇状地」として形成されてきました。また、松川を流れる水は酸性が強く、米を育てるには不向きな水質でした。そのような条件の中で先人たちが栽培を始めたのが、現在も町の特産として生産されている「小布施栗」です。
室町時代にはすでに栽培されていたと言われる小布施栗は、現在の林自治会を中心に生産され、江戸時代には幕府への献上栗として守られました。江戸時代末期には様々な加工方法が開発され、多数の栗菓子屋が生まれました。
扇状地の地形と夏冬の寒暖差、長い日照時間は、栗に限らず、りんご、梨、さくらんぼ、ぶどうなど、様々な果樹生産に適した条件を小布施にもたらし、現在でも果樹を中心とした農業がさかんな町となっています。
「千両堤」が開いた町の未来
松川を舞台に、戦国時代末期から江戸時代初期に、現在の小布施の地理的骨格を決定付けた歴史的事業の一つである大規模な築堤事業が行われています。
現在は町の南側、隣接する須坂市との境を流れ千曲川にそそぐ松川ですが、それ以前は町中心部を通り、北西側(現在の松村・六川・中条・清水自治会)に流れ、たびたび氾濫しては住民に大きな影響を与えていました。松川築堤事業では、町の南東部に「千両堤」が築かれ、松川を現在の流路に変更する大規模な土木工事が行われました。その結果、川の氾濫が激減し、氾濫を恐れて活用されてこなかった小布施の土地に、新たな可能性がひらかれたのです。
小布施「町組」と「六斎市」の誕生
千両堤ができたことで、松川の氾濫は大きく減少し、それまで荒地だった小布施の土地に、新しい可能性が生まれました。谷街道、谷脇街道、千曲川など、新潟方面と関東などの地域をつなぐ様々な道の結節点となっていたことも、その動きを後押ししました。
17世紀初頭には、谷街道沿いに上町、東町、中町、横町、伊勢町など、現在も町の商業の中心を担っているエリアに新しい村が作られ、小布施の中からはもちろん、様々な地域から移住者を受け入れました。
現在も「町組」と呼ばれるこのエリアには、1640年代に「六斎市」と呼ばれる市(マーケット)が生まれ、月6回、3と8がつく日に開かれました。18世紀後半には、六斎市は北信地域最大の市として栄え、多くの人や商品、諸国の情報がこの町に集まるようになったと言われています。
交流の町の歴史 ~高井鴻山と葛飾北斎~
六斎市の誕生とそれによる経済的な成功は、この地域に多くの豪農・豪商を生みました。彼らの多くは新しい情報や知識、技術を持った他地域の人々との出会いを好み、小布施の地で様々な交流が育まれました。
現在の六川自治会がある地域では、当時の武士階級や豪農、寺住職らが集った「六川吟社」と俳諧小林一茶との交流があったことが知られています。
また、江戸時代末期に小布施を拠点に豪農・豪商として活躍した高井鴻山は、自宅にサロンを開き、諸国の様々な文人との交流を楽しむとともに、晩年の葛飾北斎を小布施に招き入れ、作品制作を支援しました。鴻山と北斎の交流により、北斎晩年の傑作として世界的な評価を得ている東町祭屋台天井絵「龍図」「鳳凰図」、上町祭屋台天井絵「男浪図」「女浪図」などの作品が小布施に残されました。
明治維新後の衰退、それでも絶えない「新進」の気風と交流文化
江戸時代後期に繁栄した小布施ですが、明治維新後も先進的な挑戦は続きました。1873年には高井郡で初めてとなる製糸工場「雁田製糸工場」が創業されるなど、工業化が進む時代の流れをいち早くつかみ、1878年まで郡下の生糸生産1位を誇りました。
しかし、須坂市における製糸業の急激な発展によりその地位を明け渡し、産業革命や交通革命などの進展により、六斎市など町の商業を支えた市も次第に衰退していきました。以降、小布施は経済的に厳しい時代を迎えます。
そのような状況においても、小布施がもつ新進の気風は、失われることなくこの地域に流れ続け、新しい取り組みを生み出し続けます。
1932年には、現在の新生病院の原型となる「新生療養所」がつくられました。当時不治の病と言われた結核患者を受け入れる施設建設は様々な地域で反対運動による計画中止を余儀なくされていました。しかし、小布施は32番目の候補地としてその計画を受け入れました。療養所はカナダ聖公会によりつくられ、そのスタッフの多くがカナダ人などの外国人でした。多くの町民が、彼らの洗練された生活様式に影響を受けたと伝えられています。
また、第二次世界大戦中には、町は多くの疎開住民を受け入れましたが、彼らをお客様として迎えるのでなく、町をつくる町民の一人として受け入れ、協働した姿が今に伝えられています。1945年に小布施に疎開し、戦後の民主化の中で初代公民館長として活躍した林柳波は、その象徴的な存在として現在でも小布施町民の尊敬を集めています。
このような新進の気風が、1960年代以降の小布施のまちづくりにつながり、現在の小布施を形づくる土台となっています。