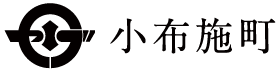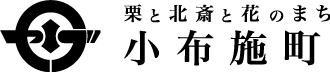制度の概要
国の経済対策に基づき、令和7年1月1日時点で小布施町に住民票があり、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた人等に対して給付金を支給します。なお、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、<不足額給付1>と<不足額給付2>の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なりますので、確認してください。
不足額給付の実施主体
令和7年度個人住民税課税団体(令和7年1月1日現在の住所地市区町村から支給されます)
不足額給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。
不足額給付1
・令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。
対象となり得る例
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
・令和6年中に扶養親族が増えた場合など
算出方法
- 不足額給付時調整給付所要額の算出
(1)所得税分控除不足額の算出(実績)
3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年分所得税額(減税前)=所得税分控除不足額
(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額の算出
1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額
(マイナスの場合は0)
(3)(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げる
2.不足額給付支給額の算出
1(3)不足額給付時調整給付所要額−当初調整給付支給額(注1)=不足額給付額(マイナスの場合は0)
(注1)令和6年度に支給対象であった人は、町から送付された調整給付金支給確認書により確認することができます。支給対象ではなかった人は0円となります。
不足額給付1の算出例(実際の税額等とは異なります)
例1
納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分所得税額(減税前)7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)2万5千円、当初調整給付金額5万円の場合
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=4万円
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円−令和6年分所得税額(減税前)7万3千円=4万7千円 - (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額4万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万5千円=1万5千円 - (3)不足額給付所要額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は7万円となります。 - (4)不足額給付金額
不足額給付所要額:7万円−当初調整給付金額:5万円=2万円
不足額給付金額は2万円となります。
例2
令和6年12月25日に子が生まれ、今まで0人だった扶養親族が1人に増えた。自身の令和6年分所得税額5万5千円、令和6年度個人住民税所得割額2万円、当初調整給付金額0円の場合。
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数1人)=6万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数0人)=1万円
(注)扶養親族の基準日は所得税が令和6年12月31日、住民税が令和5年12月31日となります。
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額6万円−令和6年分所得税額(減税前)5万5千円=5千円 - (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額1万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万円=−1万円
→マイナスの場合は0円となります(控除不足額無し)。 - (3)不足額給付所要額
(1)所得税分控除不足額:5千円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=5千円
1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は1万円となります。 - (4)不足額給付金額
不足額給付所要額:1万円−当初調整給付金額:0円=1万円
不足額給付は1万円となります。
不足額給付2
・1人当たり定額4万円を支給します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
・以下の①~③の全ての要件を満たす人
①令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
③令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)
申請方法・支給時期など
給付の対象となる人には、令和7年9月下旬から順次、通知または確認書を発送します。内容を確認し、手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。
詐欺に注意してください
定額減税補足給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にして注意ください。給付金の支給にあたり、町や国の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。