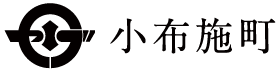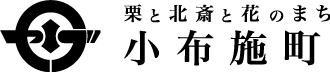介護サービス事業者が町に提出する給付関係書類(様式)がダウンロードできます。
提出先・問い合わせは、各項目を確認してください。
ケアプラン作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)または、小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
ケアプラン作成・介護予防ケアマネジメント 依頼(変更・終了)届出書 (ワード 2.5MB)
ケアプラン作成・介護予防ケアマネジメント 依頼(変更・終了)届出書 (PDF 848KB)

居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所共通の様式です。
被保険者との契約(事業所の変更・作成終了)後、速やかに提出してください。
過誤調整
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)
提出期限:各月5日(5日が閉庁の場合は直前の開庁日)
※電子メール提出可能
小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係:fukushi@town.obuse.nagano.jp
審査が確定した介護給付費について、請求誤り等の理由で事業者が保険者に対して請求実績を取り下げる場合に提出してください。
介護給付用と総合事業用にシートが分かれています。
要介護・要支援認定に係る資料提供(事業者用)
提出先・問い合わせ:小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
要介護認定等資料提供申出書(事業者用) (ワード 39.5KB)
要介護認定等資料提供申出書(事業者用) (PDF 135KB)

提供は、本人承諾のうえ、契約している介護保険サービス事業者、成年被後見人の法定代理人に限られます。
コピー代、郵送料金をご負担いただきます。
介護保険施設 入所(入院)・退所(退院)連絡票
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)
施設入所(居)・退所(居)連絡票 (ワード 21KB)
施設入所(居)・退所(居)連絡票 (PDF 94.8KB)

小布施町の被保険者が、介護保険の関連施設に入退所した場合(短期入所を除く。グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等を含む)、町に提出してください。
町外の住所地特例施設の場合は、所在地の市町村にも提出してください。
特に住所地特例に該当して提出がない場合、被保険者資格に影響することがあります。
福祉用具の貸与に関すること
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付に関する取扱い)
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)または、小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
提出時期:貸与開始前(末期がん患者の急な退院等により早急な対応が必要な場合等は必ず事前にご相談ください。)
軽度者に対する福祉用具貸与を要する例外給付に関する理由書
様式1:車いす (ワード 31.6KB), 様式1:車いす (PDF 194KB)
様式2:移動用リフト (ワード 29.8KB), 様式2:移動用リフト (PDF 146KB)
様式3 (ワード 28.6KB), 様式3 (PDF 149KB)

軽度者(要介護1、要支援1及び2の者。ただし自動排泄処理装置については要介護2及び要介護3の者も含む)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト(つり具の部分を除く)」及び「自動排泄処理装置」については、原則として算定できません。
例外的に算定が可能な場合の事務手続きについては、下記のガイドラインを確認のうえ、理由書及び関係書類を高齢者福祉係または地域包括支援センターに提出してください。
貸与期間の終了日は要介護認定の有効期間満了日です。
貸与期間の更新、貸与品目・介護度・担当の居宅介護支援事業所等に変更がある場合は再提出してください。
(ガイドライン)軽度者に対する福祉用具貸与 例外給付に関する取扱いについて (PDF 742KB)
介護保険福祉用具における同一品目の複数貸与の取り扱いについて
介護給付による福祉用具の同一品目複数貸与は、利用者の自立支援を阻害するおそれがないか、総合的な角度からアセスメントを行い、サービス担当者会議で真に必要と了承された場合に限りケアプランに位置づけてください。
この過程を経た福祉用具の同一品目複数貸与については、町への届出は原則不要(軽度者への例外給付を除く)です。
ただし、介護保険給付適正化の観点から、「複数貸与が必要と想定される理由」以外で介護給付により同一品目を複数貸与する場合は、町に理由書の提出が必要です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える理由書
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)または、小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
提出時期:
A短期入所サービスの長期利用が見込まれる時(利用開始時)
B利用が認定有効期間のおおむね半数を超える見込みがある月の前月(Aを提出済みの場合は不要)
短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える理由 (ワード 22.7KB)
短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える理由 (PDF 143KB)

居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づける場合、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な運用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置付けることが可能であるとされています。
このことから、短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する必要がある場合においては、その必要性を確認する必要があるため、 必ず理由書と必要書類をご提出ください。
添付書類など、詳しくは「短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える理由書の提出について」 (PDF 113KB)をご覧ください。
訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランの届出
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)または、小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
提出時期:基準回数を超えるケアプランを作成又は変更した月の翌月末まで
【例:訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を上回るものを位置付けたプラン作成年月日が9月25日で、プラン開始が10月の場合は、11月30日まで】
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (ワード 24KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (PDF 113KB)
添付書類:居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出可

利用者の自立支援・重度化防止等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランは、保険者への届出が必要です。
届出は、サービス内容見直し時期(要介護認定の更新又は変更、長期目標などの見直し、生活援助の回数変更など)に提出してください。利用日変更など軽微な変更の場合は不要です。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き、生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算を算定している場合)は含みません。
参考資料
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について (PDF 175KB)
介護保険最新情報Vol.637「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について (PDF 547KB)
介護保険最新情報Vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について (PDF 3.92MB)