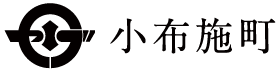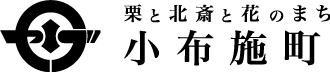このページでは、介護保険のサービスを利用したり、保険給付や利用料等の軽減を受けるために必要な町(介護保険を運営する保険者)に提出する申請書などの様式がダウンロードできます。
提出先・問い合わせ:小布施町役場健康福祉課高齢者福祉係(☎026-214-9108)または、小布施町地域包括支援センター(☎026-242-6680)
ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)による電子申請が可能なものがあります。
ただし、新たに要介護・要支援認定申請をする場合は、適切なサービス利用に速やかに結びつけるため、来所・対面による申請を推奨します。

介護保険制度や利用できるサービスなどについて(解説)
介護保険制度やサービス、利用料などについての解説は、介護保険制度のチラシ(PDF)、1~5の厚生労働省介護サービス情報公表システムのページをご覧ください。
1.介護保険とは
2.サービス利用までの流れ (参考)要介護状態区分別の状態像 (PDF 167KB)
4.介護サービスの種類や利用者負担の目安:公表されている介護サービスについて
5.身近な介護事業所・生活関連情報を探す:介護サービス情報公表システム
介護保険サービスを利用するための要介護・要支援認定申請などに提出する書類
要介護(要支援)認定の新規申請と更新申請に関するもの
※現在、申請から認定結果が出るまで、審査会の開催日程の影響などで、平均1か月半程度の日にちがかかっています。ご了承ください。
要介護(更新) 認定・要支援(更新)認定申請書 (ワード 34.1KB)
要介護(更新) 認定・要支援(更新)認定申請書 (PDF 166KB)

要介護・要支援認定を受けていない人が、介護保険サービスを利用するために要介護・要支援認定を受けようとするときに提出する申請書です。
認定結果が出る前に暫定ケアプランで介護サービスを利用することが可能です。申請書を受理する際に相談をお受けします。
また、要介護・要支援の認定には有効期限がありますので、引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新申請が必要です。
有効期間満了日の60日前から受け付けます。申請書は、新規申請と同じものです。
要介護(要支援)認定の変更(見直し)申請をする場合
要介護(要支援)認定区分変更申請書 (ワード 31.3KB)
要介護(要支援)認定区分変更申請書 (PDF 168KB)

要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも更新の時期を待たずに認定の見直しを申請することができます(区分変更申請)。
介護保険のサービスを利用中の方は、区分変更申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよくご相談ください。
要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書 、区分変更申請書の記入について
要介護・要支援認定申請を取り下げる場合
認定申請取り下げ書 (ワード 33.5KB)
認定申請取り下げ書 (PDF 66KB)

死亡・転出・状態変化・その他の理由により、現在申請中の要介護・要支援認定申請を取り下げる場合に提出する申請書です。
要介護(要支援)認定の取消しを希望する場合
要介護認定・要支援認定 取消申請書 (ワード 39KB)
要介護認定・要支援認定 取消申請書 (PDF 106KB)

介護保険のサービス利用の予定がなく、他の制度の利用希望がある場合には、介護保険の認定を取消することができます。なお、取消申請の日以降介護保険のサービスを利用することはできません。また、一度取消を行った認定に対して取消を求めることはできません。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのみを利用する場合の基本チェックリスト
要支援認定を受けずに、このチェックリストで生活機能の低下が見られる方は、事業対象者として訪問型サービス、通所型サービスなどの介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することができます。
一般的には、相談をお受けするなかで、基本チェックリストを受けていただくことを提案しています。
要介護・要支援認定に係る情報提供(被保険者本人・家族向け)
要介護認定等資料提供申出書(本人・家族用) (ワード 43.5KB)
要介護認定等資料提供申出書(本人・家族用) (PDF 99.6KB)

要介護・要支援認定を受けた被保険者本人又は家族(配偶者及び3親等以内の親族に限る)の方向けに、認定調査や主治医意見書等の情報を提供します。利用目的によっては提供が出来ない場合があります。
介護保険被保険者証等の再発行、介護保険に関する通知等の送付先変更に関する届け出
被保険者証等の再発行が必要なとき
被保険者証等再交付申請書 (ワード 37KB)
被保険者証等再交付申請書 (PDF 73.4KB)

紛失などにより、被保険者証、負担限度額認定証、負担割合証等の再発行を希望する場合に提出する申請書です。
町が被保険者に送る介護保険の書類について、本人以外への郵送を希望するとき
介護保険・後期高齢者医療関連通知等送付先変更届 (ワード 47.5KB)
介護保険・後期高齢者医療関連通知等送付先変更届 (PDF 144KB)

町は、被保険者に保険料や要介護・要支援認定、給付に関するお知らせを送付します。
被保険者とは別にお住いの親族等に送付を希望する場合に提出する書類です。裏面の注意事項を確認したしたうえでご提出ください。
在宅サービスを利用するためのケアプラン作成に関するもの
ケアプラン作成・介護予防ケアマネジメント 依頼(変更・終了)届出書 (ワード 2.5MB)
ケアプラン作成・介護予防ケアマネジメント 依頼(変更・終了)届出書 (PDF 848KB)

要介護・要支援認定を受けた人、または事業対象者が在宅サービスを利用する際のケアプランを作る事業者(ケアマネジャー)が決まったときや変わったとき、ケアプラン作成を終了するときに提出する届出書です。
居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所共通の様式です。
事業所との契約(事業所の変更・作成終了)後、速やかに提出してください。
低所得者の介護保険サービス利用料等の軽減に関するもの
施設サービス、短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)の利用者負担の軽減
介護保険負担限度額認定申請書 (ワード 107KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 180KB)
【記入例】介護保険負担限度額認定申請書 (PDF 255KB)

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の施設サービス及び短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)では、サービス費用(1割~3割負担)の他に、食費、居住費(居室料金)、日常生活費が必要です。
利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額=施設における1日あたりの食費・居住費の平均的な費用を勘案した額)が定められています。
食費:1,445円、居住費:2,066円(ユニット型個室)~437円(多床室(老健・医療院等))
低所得の人は、施設(ショートステイ)利用が困難にならないように、申請により食費と居住費の一定額以上が保険給付されます。負担限度額認定証が交付されると、所得に応じた負担限度額までを支払うことで施設サービス(ショートステイ)を利用することができます。
対象者等は、厚生労働省介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」<特定入所者介護サービス費(補足給付)>をご覧ください。
なお、令和6年8月から居住費の負担限度額が変更になり、一日60円上がっています。詳しい金額は、こちらのチラシ (PDF 253KB)をご覧ください。
小布施町福祉基金を活用した在宅サービス利用料の助成(小布施町社会福祉協議会介護保険利用料助成金)
小布施町社会福祉協議会介護保険利用料助成金給付対象確認申請書 (ワード 52KB)
小布施町社会福祉協議会介護保険利用料助成金給付対象確認申請書 (PDF 88.6KB)

低所得世帯の在宅介護を支援するため、小布施町社会福祉協議会では、運用している福祉基金を活用した助成を行っています。
住民税非課税世帯が在宅介護サービスを利用した場合の利用料の半額を助成します。(実費相当分やショートステイでの食費・居住費は除く)
対象になるサービスなど詳しくは、「介護保険在宅サービス利用料の助成(町福祉基金事業)」のページをご覧ください。
福祉用具を購入したとき
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (ワード 24.9KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDF 133KB)

都道府県等の指定を受けている事業者から福祉用具を購入した後、下記の書類を添えて申請してください。
- 領収証
- 福祉用具のカタログ(パンフレット)
- 福祉用具専門相談員が作成した「福祉用具サービス計画書」の写し
(「福祉用具サービス計画書」の写しがない場合は、申請書に福祉用具が必要な理由を詳しく記載してください) - 排泄予測支援機器の場合は、膀胱機能に係る医学的な所見が分かる書類
- 破損、経年劣化などにより再購入する場合は、破損箇所が分かる写真
いったん被保険者が購入費を全額負担し、負担割合分(1割~3割)を除いた金額が支給されます。
対象の福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 排せつ予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用のいす、浴槽内の手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
一度購入した福祉用具の再支給は、すでに購入した福祉用具が破損した場合や、利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合に限ります。(支給対象となるか、事前にお問い合わせください)
以下の品目については、購入のほか貸与を選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
当町では、福祉用具貸与・福祉用具販売については、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)で「貸与」「購入」のマークが掲載されている商品を対象としています。
都道府県等の指定を受けている事業者は、厚生労働省介護サービス情報公表システムから検索することができます。
同一の福祉用具を複数購入する場合
福祉用具の購入は、同一品目について原則1点に限り認められています。
しかし、スロープ、ロフストランドクラッチ(ロフストランド杖)につきましては、種目の性質上から複数個の利用が想定されます。
これらを複数購入する場合は、「福祉用具サービス計画書」にその必要性が記載されていることを確認してください。
住宅の改修をするとき
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときは、改修費用の一部が支給されます。
対象の住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1.~5.に伴い必要な住宅改修
改修の着工前と完了後の2回の申請が必要です。申請及び承認前に着工すると対象になりません。
住宅の改修を検討している場合、まずはケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センター(☎026-242-6680)にご相談ください。
住宅改修の内容確認、審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って申請してください。
いったん被保険者が改修費を全額負担し、負担割合分(1割~3割)を除いた金額が支給されます。ただし、住宅改修施工業者の了解のもと、受領委任払い(被保険者が住宅改修施工業者に負担割合分のみを支払い、残りの改修費は住宅改修施工業者に支払われる方法)を希望する場合は、着工前の申請の際に、「受領委任払い承認申請書及び委任状」も併せて提出してください。

着工前の申請に必要な書類
- (工事前)住宅改修工事届出書 (ワード 52KB)
(工事前)住宅改修工事届出書 (PDF 165KB) - 住宅改修が必要な理由書 (ワード 59KB)
住宅改修が必要な理由書 (PDF 167KB) - 工事費内訳書
- 平面図(改修後の図面に改修箇所を記入してください。)
- 改修予定箇所の写真 (改修前の日付が入ったもの。日付機能のあるカメラで撮影するか、撮影年月日を記入した黒板やホワイトボードを一緒に写し込んでください。また、写真に取り付け位置や形状等が分かるよう適宜記入してください。)
- (被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ)
住宅改修の承諾書 (ワード 29.5KB)
住宅改修の承諾書 (PDF 57.8KB) - (受領委任払い方式を利用する場合のみ)
受領委任払い承認申請書及び委任状 (エクセル 34KB)
受領委任払い承認申請書及び委任状 (PDF 77.8KB)
完了後の申請に必要な書類
- (工事後)住宅改修費支給申請書 (ワード 56.5KB)
(工事後)住宅改修費支給申請書 (PDF 163KB) - 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
- 工事後の日付入りの写真
なお、高齢者にやさしい住宅改良事業補助金と併用ができる場合があります。小布施町地域包括支援センター(☎026-214-6680)でご相談をお受けします。